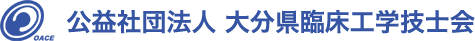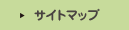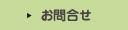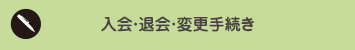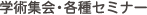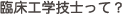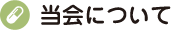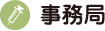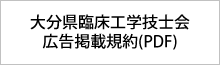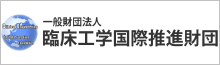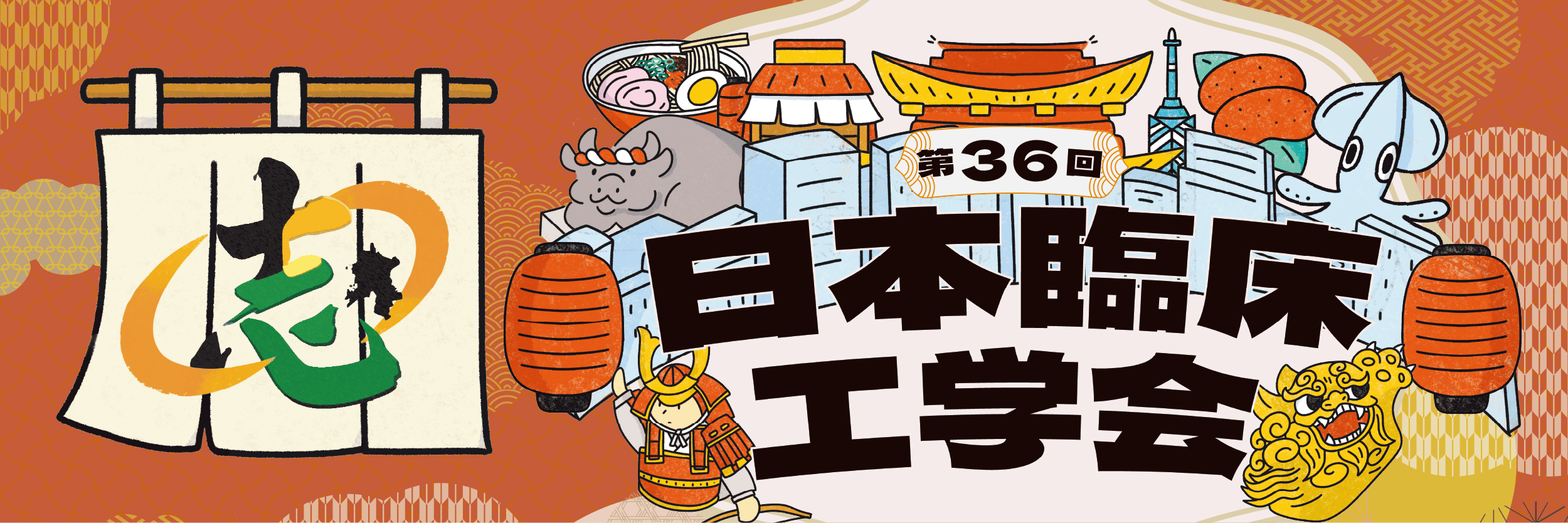公益社団法人大分県臨床工学技士会は、生命維持管理装置の操作と保守点検と多様化する医療機器の安全確保を担う専門職の団体として、臨床工学に関する知識の普及・啓発ならびに会員の学術技能の研鑽および倫理の高揚を図り、大分県における福祉、医療の発展に寄与することを目的とした非営利職能団体です。
理事長あいさつ
革新の精神を形に――2027年を見据えた「実行と研鑽」の一年
公益社団法人大分県臨床工学技士会 会員皆様へ
新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、輝かしい2026年の幕開けを健やかに迎えられたことと、心よりお慶び申し上げます。日頃より、本会運営に対し多大なるご支援とご協力を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
世界情勢は依然として流動的であり、日本の医療現場においても、絶えず変化への対応が求められております。2024年の挨拶では、AIが進化する時代だからこそ、人間が持つ「美意識や個性、独自性」を磨き、発想豊かな技士会運営を志向してまいりたいと申し上げました。2026年は、この革新的な精神を、臨床工学技士の専門職能を具体的に高める「実装の年」と位置づけたいと存じます。
喫緊の課題として、医療安全と業務効率化を両立させる「タスク・シフト/シェアに伴う告示研修」の受講が、全臨床工学技士に求められております。本研修の実施期間(コア期間)は2027年3月までと期限が定められており、これは我々の職務権限を拡大し、未来の医療を支えるために厳守すべき重要な責務です。未受講の皆様におかれましては、各自の専門的地位を確固たるものとするため、本研修の早期完了に向けた計画的な受講を強くお願い申し上げます。
1月には副理事長である田邊裕司学会長の下、第20回九州・沖縄臨床工学会および第17回大分県臨床工学会が開催されます。本学会では、秋澤忠男先生をはじめとする高名な諸先生方による講演や、学生企画を含む90演題以上の発表が行われます。AI活用における最新の知見やタスク・シフト/シェアの取り組みを深く学べるだけでなく、子育て世代の悩みやワーク・ライフ・バランスをサポートする企画も用意されております。この重要な学会を、新年の学びのスタートラインとして積極的にご活用ください。
本会は大分県、大分人工透析研究会、ならびに関連医療機関との連携を密にし、会員の皆様が安心して専門性を最大限に発揮できる環境整備に尽力いたします。理事一同、皆様の業務を支えるべく、不退転の決意で活動してまいる所存です。私自身も先頭に立ち、皆様の専門分野でのご活躍を全力で後押しいたします。
2026年が、会員の皆様にとって専門的成長と公私にわたる充実の年となりますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
公益社団法人大分県臨床工学技士会
理事長 小川 一
理事一覧
| 役名 | 担当職務 | 氏名 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 小川 一 | 医療法人聡明会 児玉病院 | |
| 副理事長 | 災害・組織・広報 | 田邊 裕司 | 帰巖会 みえ病院 |
| 副理事長 | 学術・渉外 | 中田 正悟 | 大分大学医学部附属病院 |
| 理事 | 事務局 | 高畑 智浩 | 大分医師会立アルメイダ病院 |
| 理事 | 学術 | 阿部 豪介 | 大分赤十字病院 |
| 理事 | 学術 | 尾立 拓弥 | 大分県厚生連 鶴見病院 |
| 理事 | 渉外 | 佐藤 大輔 | 大分県立病院 |
| 理事 | 組織 | 河野 圭将 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 南海医療センター |
| 理事 | 広報 | 竹中 理恵 | 社会医療法人 敬和会 大分岡病院 |
| 理事 | 災害 | 矢野 宏貴 | 国立病院機構 別府医療センター |
| 監事 | 垣迫 浩昭 | 医療法人清栄会 清瀬病院 |
定款
透析技術認定士、呼吸療法認定士の取得、更新に必要な点数について
3学会合同呼吸療法認定士
認定講習会 受講資格
過去5年以内に、認定委員会が認める学会や講習会などに出席し、12.5点以上の点数を取得すること。
認定更新制度
認定更新は定められた期間内に合同専門委員会に申請し、認定される事により行なわれます。 5年毎に認定の更新を必要とし「呼吸療法認定士認定更新に必要な点数取得基準」に記された学会・講習会等への出席および論文発表などによって総得点50点以上を取得し、取得点数証明書など更新手続きに必要な書類一式を認定委員会へ提出すること
詳しくは http://www.jaame.or.jp/koushuu/kokyu/k_index.html
透析技術認定士
認定更新の基準
透析技術認定士の更新希望者は認定証の始めの日から更新申請日までの間に、透析療法合同専門委員会で規定する当委員会の母体学会学術集会に1回以上出席していること。
認定証の始めの日から更新申請日までの間に、透析療法合同専門委員会が規定する学会、講習会などに出席する事により点数を取得し、取得点数の合計が5年更新で50点以上であること。
詳しくは http://touseki.jaame.or.jp/
上記、認定資格では、取得・更新に必要な点数の取得基準が設けられています。今後、公益社団法人 大分県臨床工学技士会では、これら認定資格に必要な点数の確保に努めてまいります。是非ご参加ください。